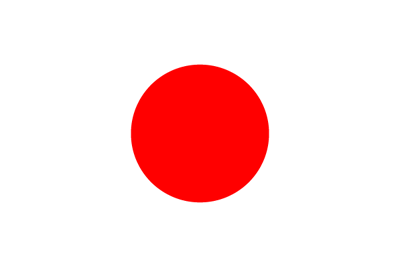Wisp
If Not Winter
Wisp
If Not Winter
- release date /2025-08-01
- country /US
- gerne /Alternative Rock, Dream Pop, Grunge, Shoegaze, Slowcore
サンフランシスコ出身のシューゲイズ・アーティストWisp(本名:Natalie R Lu)の1stフルアルバム。Billie Eilish、Kendrick Lamar、Lady Gagaといったトップアーティストを擁する大手レーベル Interscope Records からリリース。
Wispのバイオグラフィー:TikTok発のシンデレラストーリー
Wispのバイオグラフィーはご存知の方も多いでしょうが、先に軽くおさらいしておきます。
当時18歳のNatalie R Luが発表した“Your Face”がTikTokでバイラルヒットとなり、これを契機にInterscope Recordsと契約し、本格的にキャリアを始動。2024年にEP『Pandora』をリリースし、2025年にはCoachellaへ出演。System of a DownやDeftonesといった大物アーティストのオープニングアクトにも抜擢され、現在進行系でライブバンドとしても急速に進化を遂げています。
そんなシンデレラストーリーを含め、いまシューゲイズ好きの間で最も熱い注目を浴びているのがWispなのです。
詳しいバイオグラフィーはこちら▶Wisp『Pandora』レビュー
サウンド面の進化と制作陣
約1年の制作期間を経て完成した本作は、Wispの魅力をスケールアップし、シューゲイズの限界を拡張する冒険心に満ちた作品となりました。ミキシングはLars Stalfors(St. Vincent、Soccer Mommy)とStephen Kaye(Laufey、Ziggy Marley)、マスタリングはRuairi O'Flaherty(Phoebe Bridgers、boygenius)が手掛け、音質が飛躍的に向上。歪んだギターが炸裂しても耳障りにならず、シューゲイズらしい儚いウィスパーボイスの細部まできちんと聴き取れます。前作『Pandora』と聴き比べると一目(耳)瞭然ですね。
注目曲ピックアップ
#1 “Sword”
フォーク調のギターと霧のように儚い歌声でゆったりと幕を開け、突如として力強いドラムが加わり、一気に轟音を解き放つ。夢心地のリスナーを一瞬で現実に引き戻し、物語の始まりを鮮烈に告げるオープナー。
#5 “Guide light”
My Bloody Valentineを彷彿とさせるサイケデリックな轟音シューゲイズ。徐々にダウンテンポになり、ヘヴィさを増していく展開は、重轟音好きなら歓喜不可避。
#7 “If not winter”
スロウコア風にしっとりと離別の哀しみを綴る。アウトロの切ないピアノが追い打ちのように涙を誘う。
#8 “Mesmerized”
Wispとしては珍しいアップテンポなナンバー。サビメロの飛翔感がたまらない。
#9 “Serpentine”
柔らかな叙情とキャッチーさのバランスが光る一曲。歌メロには the brilliant green や大野愛果など、90〜00年代のJ-POPの香りもかすかに漂う。
#11 “Black swan”
再びKrausと手を組んだWisp史上トップクラスのヘヴィシューゲイズで、本作のハイライトの1つ。轟音を切り裂く美しいボーカルに息を呑む。前作のKrausプロデュース曲『Pandora』と対になる配置なのも興味深い。
#12 “All i Need”
アコースティック調の牧歌的なナンバー。雪解けを経て、緑豊かな草原へと歩みだした─そんな光景が浮かんできます。
多彩なプロデューサー/コンポーザーが参加しているのに世界観が全くブレないのは、まさにプロの仕事。一連のミュージックビデオも、Wispがお城で助けを待つヒロインに扮したり、甲冑をまとった騎士へと変わったりと、ファンタジックな世界観で統一されています。これもアルバムの物語性を強固にしている要因の1つでしょう。(『Pandora』では天使の姿でしたね)
シューゲイズ界への貢献と未来予測
新たな挑戦を取り入れつつ、Wisp流のシューゲイズをとことん磨き上げた珠玉の12曲。個人的にかなりハードルを上げて臨みましたが、『Pandora』を遥かに凌駕するほどの感動がありました。ヒット曲“Your Face”誕生の経緯から、『Pandora』では批判も少なからずありましたが、本作では全曲にコンポーザーとしてNatalie R Luの名前がクレジットされており、制作に深く関わっていることは明白。TikTokが創り上げたスターだと揶揄するのは、もはやナンセンスでしょう。本年度、いやここ数年のシューゲイズ界を代表するにふさわしい傑作。
きっと20年代のシューゲイズ(ニューゲイズ)・ブームのマイルストーンとして後世に語り継がれると思いますが、この作品以後、レッドオーシャン化したニューゲイズがさらに加熱するのか、あるいは収束するのか。いちリスナーとして非常に興味があります。今後の指標となることは確かですが、これを超えるのは並大抵ではなく、業界全体にどれほどの影響を与えるかはまだ未知数。もしかすると、いま私たちは歴史の転換期に立ち会っているのかもしれません。
来日公演への期待、そして次章へ
TikTokのいちシューゲイズ好きだった人物が、ひょんなことから作り上げた一曲が鬼バズり、大手レーベルに見初められ、世界各地をツアーで巡りながら、デビューアルバムを世に送り出す。なんというシンデレラストーリーでしょう。
しかし、これにてハッピーエンド……と言うにはまだ早すぎます。あくまでWispの第一章が終わったばかり。レーベルのバックアップを受けて、コアなシューゲイズ好きだけでなく、ジャンルにこだわりのない一般の音楽リスナーの元にも届き、その反響は厳正に分析されるでしょう。その結果は、シューゲイズ界全体の今後の運命をも左右しかねません。リリース直前のSpotify月間リスナー数は307万。ここからどう推移するのか注目したいところです。
私はいちファンとしてWispの成功と繁栄を祈るばかり……そして、来日公演が実現する日を心待ちにしたいと思います。
さて、冬(Pandora)を乗り越え、春(If Not Winter)を迎えたWispが次に向かうのは、やはり『夏』でしょうか? とことんポップでキャッチーなWispも見てみたいものです。夏への扉は、“Mesmerized”ですでに開かれた……そう感じるのは気が早いでしょうか。
前作のレビューはこちら▶Wisp『Pandora』レビュー

Hermyth
Aether
Hermyth
Aether
- release date /2025-03-07
- country /Italy
- gerne /Ambient, Doom Metal, Doomgaze, Drone, Post-Rock, Shoegaze
イタリアのコズミック・ドゥームゲイズ・デュオ、Hermythの2ndアルバム。
Hermythは2021年に、Nick Magister(ギター、シンセ、ドラム)とTherese Tofting(ボーカル)によって結成。NickはGhostheart Nebula、ThereseはFuneral Voidといったドゥームメタル系バンドの出身であり、Hermythにもその要素が色濃く受け継がれています。なお、「Hermyth」は、おそらくギリシャ神話の神・ヘルメス(Hermes)と神話(Myth)を掛け合わせた造語と推測されます。
本作のタイトル『Aether』(エーテル)は、古代において天空を満たすと信じられていた第五元素を意味しています。現在では科学的に否定されているものの、「この世のものとは思えない美しさ」を表す言葉として、今なお象徴的に使われています。
荘厳なキーボードと美しいギターにThereseの幽玄なボーカルが調和したサウンドは、まさにエーテルの名にぴったり。一方で、1stアルバムに比べるとギターのトーンに煌めきが増し、ボーカルの存在感もより前に出ているため、シューゲイズらしい溶け込むような感覚はやや控えめになった印象です。
とはいえ、近い音楽性を持つISONに比べると、曲の尺は短めで、歌メロ重視の展開となっているため、ドゥームゲイズやポストロックを「長くて退屈」と感じる人にもしっくりくるはずです。
ここからはお気に入りの曲をピックアップ。
#1 “Heavens”
星々の煌めきを宿したギター、恒星が放つ光の波のようなシンセ、儚く美しい歌声が織りなす天上の調べ。まるで幽体離脱して星間飛行をしているかのようなスピリチュアルな感覚を味わえます。日本の有名な曲に例えるなら、渡辺典子『火の鳥』をドゥームゲイズ化したらこんな感じかもしれません。
#2 “Aether”
民族音楽や伝統音楽由来のエキゾチシズムが感じられる神秘的なナンバー。古代の人々が星々の煌めきから神話のキャラクターを見出し、敬虔な気持ちを抱いた──そんな感覚を追体験できます。
#5 “Divination”
Aeonian SorrowのGogo Meloneがゲストボーカルとして参加。情感豊かにビブラートで歌い上げる姿は、Thereseとはまた異なる魅力を放っています。さしずめThereseのボーカルが青いリゲルだとすれば、こちらは真っ赤に燃えるアルデバラン。
#6 “The High Priestess”
最もアトモスフェリックで、アルバムタイトル『Aether』の世界観を濃密に味わえるナンバー。10分を超える長尺で、じっくりと浸らせてくれます。目を閉じて聴けば、満天の星空がまぶたの裏に浮かんでくるよう。
全体的にシューゲイズ要素はやや控えめになっていますが、Hermythならではの神話的宇宙観は健在。ぜひ、エーテルの海に身をゆだねて、44分間の星間旅行をお楽しみください。

Myriad Drone
A World Without Us
Myriad Drone
A World Without Us
- release date /2025-03-08
- country /Australia
- gerne /Blackgaze, Doomgaze, Post-Metal, Post-Rock, Progressive, Shoegaze
オーストラリア・メルボルン発のシネマティック・ポストメタル・バンド、Myriad Droneの2ndアルバム。
Myriad Droneは、2016年にShane Mulhollandのソロ・プロジェクトとして始動し、翌年には4人編成のバンドへと発展。1stアルバム制作以降に2名のメンバー変更があり、本作のラインナップはShane Mulholland(Gt/Vo)、Jacob Petrossian(Gt)、Simon Delmastro(Ba)、Frankie Demuru(Dr)となっています。2019年のデビュー作『Arka Morgana』は、YouTubeのポストロック専門チャンネル「Where Post Rock Dwells」で2019年のベストアルバム第5位に選出。私もレビューで絶賛した名作です。
それから6年ぶりとなる本作『A World Without Us』(私たちのいない世界)は、タイトルや映画『ピンク・クラウド』を思わせるカバーアートからして、「世界の終末」がテーマであると思われます。
サウンド面では、Shaneのクリーンボーカルが大幅にボリュームアップしているのが最大のポイント。さらにスクリームも取り入れられ、柔らかな叙情と猛々しい激情とのコントラストがより鮮明になりました。彼のクリーンボーカルは、非常に繊細で美しく、まるでSigur RósのJónsiやAlcestのNeigeを思わせます。前作でも「もっと歌唱パートが増えてほしい」と思っていたので、この変化は大歓迎。曲調もややポストロック寄りで牧歌的なムードが増しており、Alcestへの接近も感じられます。
#1 “A World Without Us”
クリーンなパートから一気に轟音とエモーショナルなボーカルが炸裂。ポストロックらしい静と動のダイナミズムで揺さぶりつつ、中間部では一転して民族調のコーラスが挿入され、ボーカルとユニゾンで盛り上がるAlcest風の展開へシフトします。10分強の長尺ながら掴みは上々。
#2 “Forlorn Hope”
ギターが轟音をブチ撒けながら、神秘的なボーカルと邪悪なスクリームが交錯する様は、まるで神と悪魔による最終戦争(アルマゲドン)。レーベルが「ポストロックとシューゲイズの要素をバランスよく取り入れながら、よりダークなサウンドを追求している」と語る通り、本作を象徴するナンバー。いや〜これは巻き添えを食らった人間の生存が危ぶまれますね。
#3 “DYHAMTTAJ”
プログレッシブなリズムワークに神々しいボーカルが飛翔する壮大なナンバー。
#4 “Longing”
繊細なクリーンボーカルを活かした優美なポストロックで、クライマックスには壮大な轟音でカタルシスを演出。
#5 “Disharmonia”
ブラストビートとトレモロギターで疾走するブラックゲイズ。クリーンボーカルが一瞬光を呼び込むも、すぐに轟音にかき消されて闇へと飲み込まれます。まるで人類が滅びに抗うさまを描いているよう。
#6 “Whereabouts Unknown”
TOOL風の変拍子&民族調のイントロで幕を開け、徐々にボルテージを上げていき、聖歌隊の合唱のような荘厳なクライマックスへと到達します。ドラムのFrankieが閃いたイントロのドラムパターンから、新メンバーがアイデアを持ち寄って完成させた新境地的名曲。「TOOL meets シューゲイズ」はまだ例が少ないながら、じわじわと観測されつつあり、いま私の中で大注目のスタイル。まさかMyriad Droneがそれをやってくれるとは、嬉しい誤算でした。今年のベストチューン最有力候補の1つ!
ラストの#7 “Valediction”は、どこか物寂しくも穏やかなメロディで、余韻たっぷりに幕を閉じます。最後に訪れたこの静けさは、人類が絶えた後の世界を示唆しているかのよう。このアルバムは、いずれ滅びゆく人類への鎮魂歌なのかもしれません。
本年度のポストロック/シューゲイズ界を代表する傑作の1つ。Sigur RósやAlcest、Holy Fawnなどのファンは、必ずチェックよろです!
前作のレビューはこちら▶ Myriad Drone『Arka Morgana』

雨の中の馬
Triste EP.
雨の中の馬
Triste EP.
- release date /2025-03-28
- country /Japan
- gerne /Alternative Rock, Dream Pop, Electronic, Shoegaze
日本のシューゲイズ・バンド、雨の中の馬による2017年発表のEP。2025年に中国のインディーレーベル『雨模様』(Amemoyo)から初のフィジカル化。あわせて公開されたサブスク版はDisc1・Disc2の2枚組仕様となっています。
雨の中の馬は、Akihiro Nio(Gt/Vo)を中心としたプロジェクトで、本作では作詞・作曲からレコーディング、ミックス、マスタリングに至るまですべて自ら手がけています。また、サポートメンバーとしてKeisuke Yoshimura(Gt/Vo)、Rintaro Yamamoto(Ba)、Saki Miyamoto(Dr)がクレジットされており、Disc1ではシューゲイズらしいノイジーでライブ感のあるサウンドを展開。#1 “Triste”は、サイレンのように狂おしく響き渡るギターノイズに、哀しげな歌声が溶け込み、メランコリック・シューゲイズの理想形といえる上質な仕上がり。甘さや痛みも内包したイノセントな声質は、ART-SCHOOLの木下理樹を彷彿とさせ、Triste=哀しみを表す曲調とよくマッチしています。
続く#2 “Dancer In The Dark”は、後期Supercarの名曲“Yumegiwa Last Boy”を彷彿とさせる轟音ダンスチューン。クールな歌メロや、「愛されたいだけ」と「触れていたい夢幻」の語感に共通点が見られるため、オマージュの可能性もありそうです。
Disc2には、宅録バージョンの音源を収録。こちらはローファイで素朴なタッチが魅力で、同じ曲でもまったく異なる表情を見せてくれます。なお、SoundCloudには1年前に新曲が投稿されており、現在も活動を継続しているようです。気になる方はぜひチェックしてみてください。
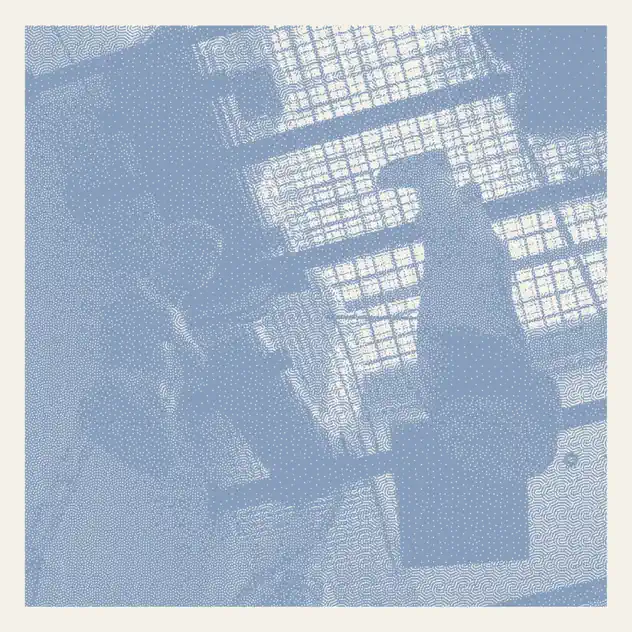
bdrmm
Microtonic
bdrmm
Microtonic
- release date /2025-02-28
- country /UK
- gerne /Alternative Rock, Dream Pop, Electronic, Industrial, Shoegaze, Trip Hop
UKのハルを拠点に活動するシューゲイズ・バンドbdrmmの3rdアルバム。前作に続き、Mogwai主宰のレーベルRock Actionからのリリース。
bdrmmは、フロントマンであるRyan Smithの宅録プロジェクトとしてスタートし、やがてバンド編成へと発展。2020年の1stアルバム『Bedroom』では、ゴスやポストパンク由来の陰りをまとったシューゲイズで注目を集め、2022年の2ndアルバム『I Don’t Know』ではアンビエントやトリップホップの要素を取り入れ、新たな魅力を開花させました。
本作『Microtonic』では、その進化がさらに加速し、BjörkやFour Tet、Massive Attackといったアーティストの影響を受け※、エレクトロニックな領域へとさらに深く踏み込みました(※Jordan SmithがClashのインタビューで発言)。パンデミック以降の不安や孤独、社会の閉塞感が色濃く反映され、かつてのようなシューゲイジーな轟音は影を潜めています。その代わり、不穏なメロディのシンセが霧のようにまとわりつき、じわじわと不安を掻き立てながらも、機械的なビートがトランシーな没入感をもたらしてくれます。彼らが提示しているのは、単なるレイブの高揚感ではなく、現実の不安を払うための逃避行為としてのダンスミュージックなのでしょう。
かなり大胆な変化で賛否両論ありそうですが、私は大歓迎! The KVBやSPC ECOといったダークでエレクトロニックなサウンドが好きな方はぜひお試しあれ。
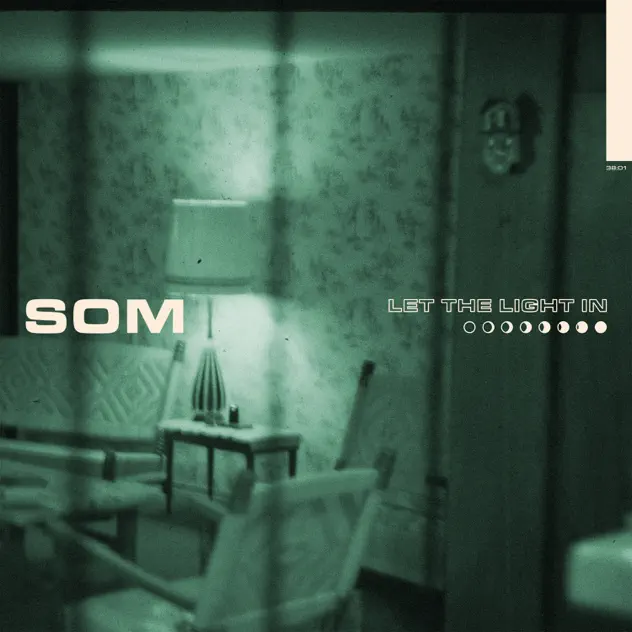
SOM
Let The Light In
SOM
Let The Light In
- release date /2025-07-14
- country /US
- gerne /Alternative Rock, Doomgaze, Post-Metal, Shoegaze
US出身のポストメタル/ドゥームゲイズ・バンドSOMの3rdアルバム。ポストメタル界の名門レーベル、Pelagic Recordsからリリース。
SOMは、Caspian、Junius、Constantsの現・元メンバーによって結成され、これまでアルバムとEPをそれぞれ2作ずつリリース。本作のレコーディング中に創設メンバーのドラマー、Duncan Richが脱退し、それに伴ってメンバー構成が変更。現在のラインナップは以下の4人編成となっています。
- Will Benoit(Vo, Ba, Gt, Electronics)
- Justin Forrest(Dr, Ba)
- Mike Repasch-Nieves(Gt, Piano)
- Joel Reynolds(Gt, Syn)
グランジやシューゲイズ、ドゥームメタル由来の重厚なギターと幽玄なボーカルの調和が生み出す陶酔的なサウンドは、メタル系の音楽メディアMetal Injectionによって「ドゥームポップ」と形容され、まるで茨の棘に絡みつく甘美な蜜のような個性的な味わいを生み出しています。2023年のEPで見せたDepeche Modeへの憧憬や、グリーンのアートワークで示されるType O Negativeへのリスペクト*もしっかりと継承されています。
※インタビューで、グリーンのアートワークがType O Negativeのオマージュであることが明かされています。また、別のインタビューでは、ボーカリストのWill Benoitがバンド初期の構想において「Type O NegativeのPeter Steeleのような圧倒的な存在感を持つキャラクター」を思い描いていたと語っています。彼自身はそのような人物にはなれないとしながらも、そのイメージは常に頭の片隅にあったとのことです。
本作では『Let The Light In』というタイトルの通り、従来のメランコリックな作風から希望の光へと歩みを進めるような変化が感じられます。パンデミック期の陰鬱なムードの中で書かれた#2 “Let The Light In”では、「光を招き入れよう」と繰り返し歌われており、その変化を象徴するナンバーとなっています。
その影響で、全体的にダークさは控えめになっており、ダークシューゲイズ目線だと少々物足りなさもありますが、静と動・光と闇のコントラストが冴える#5 “Give Blood”、退廃的で深い哀愁を放つ#8 “The Light”といったダークな楽曲たちは、かえって強く存在感を放っています。「光が強ければ、闇もまた深くなる」とは実に言い得て妙ですね。とはいえ、過去作より光のオーラが強めな点は、少々好みが分かれるところです。
10月からは、Slow CrushのUKツアーでBlanketとともに各地を巡る予定のSOM。闇の中で希望の光を見出した彼らがどんな成長を遂げるのか、とても楽しみです。いつか日本にも来てほしいですね。

Circuit des Yeux
Halo On The Inside
Circuit des Yeux
Halo On The Inside
- release date /2025-03-14
- country /US
- gerne /Darkwave, Drone, Gothic, Industrial, Neoclassical, Synth Pop
イリノイ州シカゴのSSW、Circuit des Yeux(本名:Haley Fohr)の8thアルバム。InterpolやSnail Mailを擁するMatador Recordsからリリース。4オクターブの歌声を駆使しながら、ゴシック/ポストパンク/ネオクラシカル/ダークウェイヴ/インダストリアル/フォークを自在に渡り歩くボーダーレスなサウンドが特徴。
本作ではインダストリアル色を強化し、よりダークに進化。低音とファルセットを巧みに使い分け、Chelsea WolfeやDead Can Dance、Depeche Modeが電脳世界でセッションしたかのようなシネマティックな暗黒舞踏を展開しています。
シューゲイズ好きにイチオシなのは、#4 “Anthem of Me”。荘厳なネオクラシカルとドローン風の歪んだギター、巨像の足音のような重厚なビートが見事に融合しており、ISONやLovesliescrushingといった幽玄なドローン/ドゥームゲイズ好きにもきっと刺さるはず。
ちなみに、ドローン風の音響にフォークやネオクラシカル/ダークウェイヴを融合させる試みは、最近のEthel CainやPenelope Trappesの楽曲にもいくつか見られ、個人的に注目しているスタイルの1つ。今後も積極的にご紹介していくので、乞うご期待です。

Ritualmord
This is not Lifelover
Ritualmord
This is not Lifelover
- release date /2025-03-08
- country /Sweden
- gerne /Ambient, Blackgaze, Depressive-Black-Metal, Folk, Industrial, Post-Black Metal, Post-Rock
Lifeloverの元メンバーによる新バンドRitualmordのデビューアルバム。
スウェーデンのデプレッシブ・ブラックメタル・バンドLifeloverの元創設メンバーである( )(本名:Kim Carlsson)と1853によって2007年に結成され、2020年から本格的に活動を開始しています。
Lifeloverの1stアルバムにそっくりなアートワークなのに「This is not Lifelover」(これはLifeloverじゃない)というタイトルで戸惑う方もいるかもしれません。これはLifeloverの20周年を祝いつつ、「何をしても比較されるからこそ、あえてLifeloverではない」と明言し、新たなスタートを印象づける狙いがあるようです。
実際に音を聴いてみると、アンビエント、フォーク、インダストリアルからポストロック〜シューゲイズに至るまで、多彩な要素がブレンドされていて、「確かにLifeloverではない」と納得させられます。一部の楽曲は、当初Lifeloverのために書かれたもので(実現はしなかったものの)、随所に挿入されるKim Carlssonのスクリームからは、Lifeloverの遺伝子を感じずにはいられません。しかしKatatoniaの『Brave Murder Day』直系のデプレ路線だったLifeloverと比べると、Ritualmordはもっとドリーミーで、ブラックゲイズやポストブラックの領域に踏み込んでいるのが最大の違い。Lifeloverの残滓をわずかに漂わせつつ、別の可能性──すなわち“Lifeloverオルタナティブ”とでも呼ぶべき、新たな世界観を打ち出しています。
デビュー作だけに、まだまだ模索中という印象もありますが、今後シューゲイズやポストロックの要素がさらに強化される予感もあり。Lifeloverという枷を外れて自由を得た2人が、今後どのような世界を描いていくのか非常に楽しみです。
なお、Kim Carlssonが関わるもう1つのプロジェクト、Kallも個性的な作品をリリースしているので、ぜひあわせてチェックしてみてください。

Glixen
Quiet Pleasures
Glixen
Quiet Pleasures
- release date /2025-02-21
- country /US
- gerne /Alternative Rock, Grunge, Dream Pop, Shoegaze
アリゾナ州フェニックスを拠点とするシューゲイズ・バンドGlixenの2nd EP。プロデューサーはMy Bloody ValentineやDIIVなどを手がけたSonny DiPerri。
Glixenは、2020年に結成して以来、SXSWをはじめとする多数のフェスティバルに出演し、2025年4月にはついにCoachellaのステージに立ったシューゲイズ界の超新星。現メンバーは、Aislinn Ritchie(Vo/Gt)、Esteban Santana(Gt)、Sonia Garcia(Ba)、Keire Johnson(Dr)の4人となっています。ちなみにバンド名の「Glixen」は、Lovesliescrushingの楽曲名が由来です。
砂嵐のようなノイズに、ダークで官能的なメロディを溶け込ませた重厚なサウンドが最大の特徴で、若手ながらMBVファンも唸らせる本格派のオーラを放っています。
本作は甘美さを残しつつ、さらにダークかつソリッドに深化。オープニングの #1 “shut me down” は、ドラムの連打と轟音ギターの壁で圧倒するインスト。ライブでラストを飾る定番曲となっています。日本のくゆるが好きな人にぶっ刺さること請け合いです。
イチオシは #4 “sick silent”。甘美なメロディとJesu級のヘヴィなノイズが渦巻くサウンドは、ゼクノヴァ砲さながらの破壊力。
近年のニューゲイズ勢がDeftonesやWhirrの影響下で独自進化を遂げている一方で、Glixenはその流れにMBVへの原点回帰のエッセンスを加えている印象を持ちました。新規のシューゲイズファンを原典へと導く「ジークアクス」的な循環を生み出してくれることを期待したいですね。
シューゲイズの新世代を担う存在として、Wispともども目が離せません。もし来日が実現したら、ぜひくゆると対バンしてほしいですね!
【Glixenメンバーの小ネタ集】
- Aislinn(Vo/Gt)
映画好きで、特にグレッグ・アラキ監督の『リビング・エンド』『ノーウェア』『スプレンダー/恋する3ピース』がお気に入り。1st EP収録の名曲 “Splendor” の由来にもなっている
好きなアニメは『NANA』『lain』『エルゴプラクシー』『ちょびっツ』『寄生獣』『チェンソーマン』など(妙に濃いラインアップに親近感……!) - Esteban(Gt)
元メタル畑の出身で、Godfleshがお気に入り
意外にもDead Can Danceも嗜むそう - Sonia(Ba)
2019年にベースを始めたばかりで、Glixenが初めてのバンド
好きなアニメは『鋼の錬金術師』 - Keire(Dr)
好きなアニメは『アフロサムライ』
インタビューで「日本に行ってみたい」と語っている

路傍の石
alternative mick
路傍の石
alternative mick
- release date /2025-01-19
- country /Japan
- gerne /Alternative Rock, Emo, Grunge, Post-Rock, Shoegaze
ボカロPとバンド、2つの顔を持つ東京発のアーティスト、路傍の石の7thアルバム。
前作『Pater Noster』ではブラックゲイズ/ポストブラックメタルにフォーカスしていましたが、本作では一転してエモ、グランジ、シューゲイズ、ハードコアなどを融合したオルタナティブ・ロック色の強い作風になっています。
ここではダークシューゲイズ好きにおすすめの2曲をご紹介します。
#4「僕は彼女の幽霊を見た」
冬の冷たさをまとったサッド・シューゲイズ。愛する人を失った哀しみが、心に凍傷のような痛みを刻みつける。Whirrの『Sway』が好きな方に特におすすめ。
#5「生きていてごめんなさい」
路傍の石史上、最もダークな楽曲のひとつ。自罰的なセリフが延々と綴られる中、突如として悲痛な絶叫が放たれ、儚い歌声と重なり合いデプレッシブ・ブラックメタル級の希死念慮を撒き散らす。絶叫はおそらくミクさんの声を加工したもので、『深淵に心在りて』などでも使われていましたが、これほどエグいものは初めてではないでしょうか。ボーカロイドも工夫次第でここまでの感情表現ができるとは驚きです。
ただし、あまりにも暗いため、気分が落ち込みやすい方や感受性の強い方はくれぐれもご注意ください。私も元気がないときにうっかり聴いてしまって闇に呑まれそうになりましたが、咄嗟にぼっちちゃんの電子音めいた悲鳴に脳内変換して難を逃れました(笑)
なお本作の翌月には、早くも8thアルバムがリリースされ、さらに6/17にはバンド形式での初音源も公開。創作への貪欲な熱意に頭が下がります。
今回レビューを書くにあたって、比較のために過去作もすべて履修したのですが、どれも素晴らしかったです。そろそろライブで体感してみたいですね!