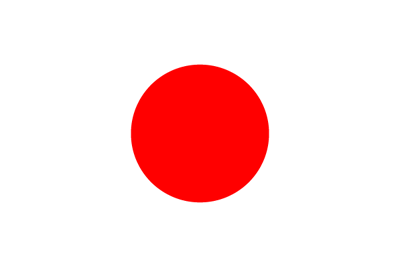くゆる
Lovescape
くゆる
Lovescape
- release date /2025-02-19
- country /Japan
- gerne /Alternative Rock, Blackgaze, Doomgaze, Grunge, Post-Rock, Shoegaze, Slowcore
東京のシューゲイズ・バンド、くゆるの1stアルバム。
2022年の結成以降、圧倒的なライブパフォーマンスで注目を集めてきたくゆる。その初のフルアルバムが本作『Lovescape』である。現メンバーは以下の5名。
- 下戸あやな (Vo/Gt)
- 飛田熙 (Gt)
- 上田隆太 (Gt)
- 河瀬塁 (Ba)
- 山口航 (Dr)
国内屈指の轟音による暴力と美の対比
サウンドの核となるのは、トリプルギターが生み出す圧倒的な轟音だ。リスナーを竜巻の中に叩き込むかのような苛烈さは、国内でもトップクラスを誇る。さらにドラムは暴力的な音の壁を貫くほどパワフルで、強靭なサウンドの屋台骨として機能している。
楽器隊の過激さゆえ、初めはシューゲイズとかけ離れた印象を持つかもしれないが、蜃気楼のように幽玄にたなびくボーカルが、くゆるを本格的なシューゲイズたらしめている。この「暴力」と「美」のコントラストはくゆるの世界観にとって欠かせない要素だ。
ジャンルを横断する多様な楽曲群
単なるシューゲイズに留まらない、ジャンルを横断する多様な楽曲群も本作の大きな魅力だ。
静と動を交錯させながら闇へ堕とす#1 “mope”。鼓膜を苛む強烈なノイズが渦巻き、やがて全てを破壊せんばかりにブラックゲイズ風の轟音へ収束する#2 “蒼い空”。スロウコアの寂寥感とドゥームゲイズの重厚さを巧みにブレンドした#7 “momo”、ポストロック譲りの展開美で広大なサウンドスケープを演出する#8 “BESIDE”など、8曲それぞれが非常に強い個性を放っている。
近年、日本ではNothingやWhirrなどをルーツとするヘヴィシューゲイズ志向のバンドが増加傾向にあるが、くゆるはさらに一歩先の未来を提示している。エクストリームなハードコアやメタルが集うイベントにも招致され、過激な轟音でオーディエンスを熱狂させている事実が、彼らが日本のシューゲイズ・シーンにおけるオルタナティブ精神の真の体現者であることを雄弁に物語っている。
くゆるの真髄はライブにあり
サウンドプロダクションはクリアで快適でありながらも、ライブに近いエネルギーを有しており、何度もライブを経験しているリスナーでも高い満足感を得られるだろう。ライブではさらに全身を切り刻むような音圧で襲いかかってくるため、未体験であればぜひ直に浴びてブッ飛ばされてほしい。きっと「くゆるはライブこそ真骨頂」だと実感するはずだ。なお耳栓は必ず持参のこと。
カバーアート考察
次はカバーアートに注目したい。
暗闇の中で目を閉じて身をくるめる姿に私は胎児を連想した。胎内で聞いている音は、母親の心臓の脈動と血流によるノイズが主であるという。絶え間ない喧騒の中で耳にする母の呼びかけや歌声は、暗闇に差し込む光のようにいっそう美しい音色として届いているに違いない。これはある種のシューゲイズ・サウンドの原型とも解釈できる。
近年のシューゲイズ・ブームは、厳しい現実から「愛にあふれる場所」=「Lovescape」への逃避、すなわち胎内回帰願望の表れではないだろうか。くゆるの音楽は、この願望を満たすためのサウンドトラックとして最適な作品である。
私に還りなさい、生まれる前に──(突然のエヴァで締め)

KRISHNV
Craving and dirges
KRISHNV
Craving and dirges
- release date /2025-12-12
- country /Japan
- gerne /Alternative Rock, Dark Ambient, Doomgaze, Experimental, Folk, Noise, Post-Metal, Post-Rock, Progressive
東京を拠点に活動するエクスペリメンタル・ロック・バンド、KRISHNV(クリシュナ)の2025年作。(ディスコグラフィーによると3rdアルバムのもよう)
KRISHNVは、Takumi Izawa(ギター/ボーカル)とShunsuke Shibuya(ベース)により2019年に結成。
彼らの音楽性を一言で表すならオルタナティブ暗黒舞踊。太古の祭祀のようなトライバルなリズムが律動する中、泥流のような轟音がゆっくりと浸食し、マントラめいた妖しい歌唱が延々と紡がれる。総じてTOOLの呪術的なリズムワークとDead Can Danceの神秘性の融合を連想させるが、日本語詞が異国の呪文のように変異して響くのは、このバンドに宿る独自の魔力に他ならない。特に19分強におよぶ#10 “Obsidian”の没入感は圧巻で、もはや一種の領域展開といえるレベルだ。
ライブではサポートメンバーを迎え、ツインドラム&トリプル(時にクアドラプル)ギターによる轟音の壁をもって観客を圧倒する。暗闇に浮かぶVJの映像をバックに身を捩りながら一心不乱に音を紡ぎ出す様は、もはや演奏ではなく儀式そのものだ。初めは不意に異界を覗いてしまったような根源的恐怖に襲われるが、音に身を委ねた瞬間、身体は自然と躍り出し、恍惚の頂へと到達するだろう。
彼らが呼び寄せるのは、聖か、邪か──その真相は、あなた自身の目と耳で確かめて欲しい。
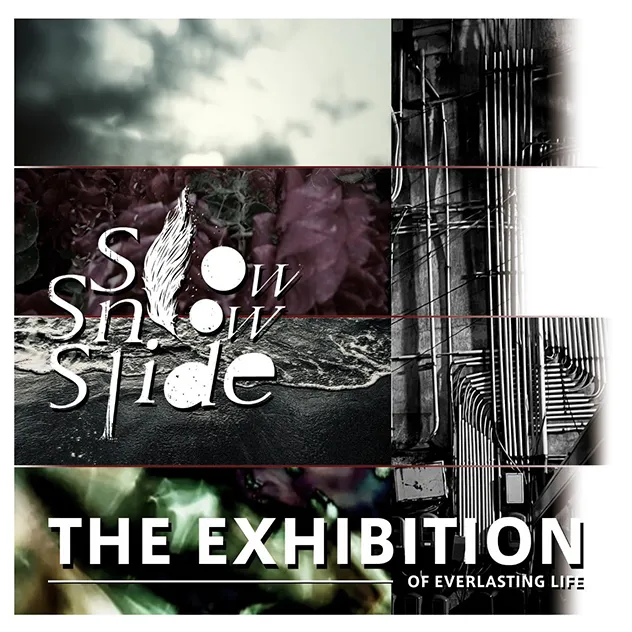
Slow Snow Slide
THE EXHIBITION
Slow Snow Slide
THE EXHIBITION
- release date /2025-05-03
- country /Japan
- gerne /Alternative Rock, Gothic Rock, New Wave, Post-Punk, Post-Rock, Shoegaze
山形県酒田市を拠点に活動するシューゲイズ・バンド、Slow Snow Slideの2ndアルバム。
2016年に本格始動し、2019年に1stアルバム『paradise lost』を発表。メンバーチェンジを経て2022年に現体制で再始動し、約6年ぶりとなるニューアルバムを完成させた。
制作時のメンバーは以下の5名。(※リリース後、MASAKUNIは脱退)
- GOE(ボーカル/ギター)
- TAKEDA NATSUKO(ギター/ボーカル)
- YAMA(ギター)
- MASAKUNI(ベース)
- YOKOCHIN(ドラム)
1stアルバムでは、ポストロックとシューゲイズを軸にピアノやヴァイオリンといったクラシカルな要素を取り入れ、既存の枠に留まらない独自の世界観を打ち出した。バンド名は「緩やかな雪崩」を意味し、持ち味である壮大なサウンドスケープを象徴している。
『THE EXHIBITION』は、ロシアの作曲家ムソルグスキーによる『展覧会の絵』に着想を得て制作。トリプルギター&ツインボーカル体制を活かし、さらに重層的なサウンドへアプローチしている。インストゥルメンタルの“Promenade”を含む全7曲は、それぞれの楽曲が異なる情景を描きつつ、まるで展示室を巡るように展開していく。
注目曲ピックアップ
#2 “Drawing on the blank page”
ダイヤモンドダストのようなアルペジオと、吹雪のような轟音ギターが交錯しながら、ワルツ調にゆるやかに展開する。ツインボーカルの美しいハーモニーによる温かな叙情は、凍りついた雪原に朝日が満ちるような幸福感をもたらす。
#3 “Luzifer”
ゴス/ニューウェイヴの黒い血が匂い立つダンスチューン。冷たいトーンのギターと、GOEの艶のある歌声が妖しく絡み合う。ドラム連打&轟音ギターのアクセントも秀逸。
#6 “Nihilistic”
ツインギターが絡み合いながら、静と動を巧みに織り交ぜた起伏のある展開で魅せる。後半は一気にダイナミックな轟音を解き放ち、エモーショナルに歌い上げながら荘厳なクライマックスへ。随所に覗くキャッチーなギターフレーズにも彼らのチャレンジ精神が現れている。
#7 “Rasen Kaindan”
歪んだベースが地を這い、黒い波動を撒き散らすダーク・アンセム。ラストは轟音とともに絶叫が響き渡り、リスナーを暗黒の奈落へと引きずり込む。
曲ごとの個性が際立ちながらも、Promenadeを軸に世界観を共有する構成は、まさに『展覧会の絵』の現代的再解釈といえるだろう。
本作は現在CDのみでリリース中(サブスク未配信)。公式オンラインショップまたはライブ会場で購入できる。ぜひ現物を入手して、壮大な物語へと誘うイマーシブ体験を味わってほしい。
Slow Snow Slideは東北〜関東の各所を巡るリリースツアーを実施中。遠方のファンにとっては、彼らのパフォーマンスを体感する貴重な機会となる。ツアー情報は公式サイトおよびSNSでチェックを。
最新情報はSlow Snow Slideの公式サイト・SNSをチェック

Cuspid
Whiplash
Cuspid
Whiplash
- release date /2025-10-15
- country /US
- gerne /Alternative Rock, Dream Pop, Grunge, Nu Metal, Shoegaze, Slowcore
ロサンゼルスと北京を拠点に活動するシューゲイズ・アーティスト、Cuspidのデビュー1st EP。
現時点で明かされているのは、DeftonesとLana Del Reyを敬愛する18歳という情報のみ。そんなミステリアスな新人が、デビュー作にして驚異的なクオリティを見せつけてきた。
ヘヴィなギターと幻想的なメロディのマッチングはWispを彷彿とさせる。しかしCuspidのボーカルはより退廃的で深みがあり、楽曲も全体的にダウンテンポかつヘヴィで、まるで海の底へ沈み込むような深いメランコリーが堪能できる。その点では、むしろGraywaveやSlow Crushに近いだろう。もしWispに「もう少しダークさが欲しい」と感じていたリスナーがいるなら、本作はまさに理想的な作品だ。
#1 “Debris”では、轟音ギターが空間を切り裂くように唸りを上げ、霧のようなボーカルが虚ろに響く──その対比の美しさに思わず息を呑む。#2 “Floor 12”では、不穏なアルペジオを散りばめながらゆったりと進行し、終盤に向けて徐々にボリュームを上げ、一気に哀しみを解き放つ。続く#3 “Flyaway”の繊細なイントロへとシームレスに繋がる展開も秀逸だ。ラストの#4 “Whiplash”はスロウテンポでメロディを丁寧に紡ぎ、深い余韻を残して幕を閉じる。全4曲、もれなく名曲レベルだ。
今後の期待も含め、当サイトのAOTY本命候補にノミネート。Wispに続く次世代のシューゲイズ・アーティストとしてぜひ抑えてほしい。現時点でのSpotifyの月間リスナーは3桁(680)だが、今後の推移に注目だ。

Keep
Almost Static
Keep
Almost Static
- release date /2025-03-10
- country /US
- gerne /Alternative Rock, Dream Pop, Grunge, Post-Punk, Shoegaze,
ヴァージニア州リッチモンド出身のシューゲイズ・バンド、Keepの3rdアルバム。
2013年に結成。初期はNickとWesのデュオだったが、徐々にメンバーを増やし、現在は以下の4名となっている。
- Wes Smithers(ギター・サンプリング)
- Will Fennessey(ベース)
- Levi Douthit(ギター・シンセ)
- Nick Yetka(ドラム・ボーカル)
The CureやThe Smashing Pumpkins、Slowdiveからの影響を公言しているが、それだけでは留まらない幅広い音楽性を備えている。1stアルバムはThe CureやDIIV譲りのドリーミーなポストパンク系が多かったが、2nd以降ではさらに多彩さが開花。グランジ系のヘヴィな轟音を軸としながらも、#8 “Sodawater”では、ギターが煌めくドリームポップ、#11 “Hurt a Fly”ではエモ風のパワフルな疾走チューンも飛び出し、単純にシューゲイズに括れないプリズムのような輝きを見せてくれる。
しかし、決して方向性が散漫にはならず、Keepの真骨頂である哀愁美はアルバムを通して揺るがない。全編に渡り、エモーショナルなボーカルに美しいリードギターが絡み合い、深い哀愁を織り上げている。メロディアスな旋律と力強いギターリフの調和は、プロデューサー/エンジニアのZac Montez(Whirr・Cloakroom)の手腕の賜物でもあるだろう。昨今のヘヴィシューゲイズ/グランジゲイズと比較してもメロディアスで聴きやすいため、入門にも最適な作品だ
今年は4〜5月に同郷の盟友Turnoverとのツアーを完遂した後、7〜9月にサマーツアー(8月はLeaving Timeと共演)、10月末からはEU/UKツアー(Slow Crushと共演)がスタートするなど、休む暇もないほどライブ活動に精を出している。今後ますます注目を集めることは確実だろう。来日にも期待したい。

Church of the Sea
Eva
Church of the Sea
Eva
- release date /2025-04-11
- country /Greece
- gerne /Alternative Rock, Doom Metal, Doomgaze, Folk, Gothic, Industrial
ギリシャ・アテネ拠点のドゥームゲイズ・バンドChurch of the Seaによる2ndアルバム。
2017年にアテネで結成。現メンバーは以下の3名。
- Irene(ボーカル)
- Vangelis(ギター)
- Alex(シンセサイザー/サンプラー)
民俗音楽の血を継ぐエキゾチックなボーカル、地を這うようなヘヴィなギター、幽玄なシューゲイズのテクスチャーが織りなす多層的なサウンドスケープが彼らの真骨頂。
本作タイトル『Eva』は創世記のイヴに由来し、新たな試みとして歌詞にギリシャ語を取り入れている。その歌声はシャーマンの詠唱のように神秘性を帯び、神話を音へと昇華している。
ハイライトは#3 “Eva”。トライバルなパーカッションにのせて神秘的なボーカルが優雅に舞い踊る。後半からドゥーム風のギターが加わって徐々にボルテージを上げていき、儀式的な高揚をもたらす。まるでDead Can Danceがドゥームゲイズ化したような荘厳なナンバーだ。
ベッドルームからエデンの園へと誘う霊験あらたかな響きはさすがギリシャ産。Dead Can DanceやChelsea Wolfe、Shedfromthebodyのファンはぜひチェックを。

Photographic Memory
I Look at Her and Light Goes All Through Me
Photographic Memory
I Look at Her and Light Goes All Through Me
- release date /2025-05-30
- country /US
- gerne /Alternative Rock, Bedroom Pop, Electro Pop, Emo Rap, Grunge, Indie Electronica, Nu Metal, Shoegaze, Synth Pop
LAを拠点とするプロデューサー/ミュージシャンMax EpsteinのプロジェクトPhotographic Memoryの2ndアルバム(Spotify準拠)。USインディレーベルdeadAir Recordsよりリリース。
Photographic Memory名義での活動は2013年に始まり、その傍らQuannnicやMilitarie Gun、Cold War Kidsなどの作品制作やライブサポートにも関わってきた。また、Wispの『Pandra』期から楽曲制作に携わり、『If Not Winter』ツアーではサポートアクトを務め、ステージ上でコラボも行うなど、多方面でその才能を発揮している。
初期はベッドルームポップやドリームポップ中心のドリーミーな作風だったが、本作ではエモ・ラップ、インディ・エレクトロニカ、ニューゲイズなど、多彩な音楽性を展開している。
注目曲ピックアップ
#8 “Clearly” ― ポーター・ロビンソンを思わせる清涼感あふれるエレクトロ・ポップ。
#10 “Born 7:7 (feat. Darcy Baylis) ” ― 幻想的なエレクトロニカとヘヴィシューゲイズが見事に融合。
#11 “Heartstyle (feat. Wisp) ” ― きらびやかなシンセをまとったエレクトロ色の強いダンスチューン。Wispの新たな一面が楽しめる。
#12 “Love In My Heart” ― ニューメタル〜グランジ風のヘヴィなインスト曲。KornやAlice in Chainsのようなゴリゴリしたギターが印象的。
#17 “Spill (feat. Kraus) ” 重厚なギターのサウンドウォールに淡い歌声が漂うメランコリックなヘヴィシューゲイズ。Krausらしさが発揮された名曲。本作のハイライト。
プロデュース経験で磨き上げられた越境性が発揮された充実作。シューゲイズの新世代アーティストの一人として、Wispとあわせ今後の動向に注目したい。

Spiine
Tetraptych
Spiine
Tetraptych
- release date /2025-03-27
- country /Australia
- gerne /Blackened Doom, Depressive Black Metal, Doom Metal, Doomgaze, Funeral Doom, Post-Rock
オーストラリアのブラッケンド・ドゥームメタル・デュオSpiineのデビューアルバム。
Spiine〜Virgin Black×Ne Obliviscarisの鬼才によるコラボ〜
Virgin BlackのギタリストSesca Scaarba(Samantha Escarbe)と、元Ne ObliviscarisのボーカリストXen(Marc Campbell)によって結成。バンド名Spiineは「背骨」を意味し、2人の背骨を結合させることで精神を強化し、彼らの音楽が描く「暗く惨めな絶望」を世界に伝える決意を表している。「i」が並ぶのは、2人が精神を預け合う象徴である。※曲名の「i」もすべて2つになっている点に注目
本作はドラムにWaltteri Väyrynen(Opeth、元Paradise Lost)、ベースにLena Abé(My Dying Bride)を迎え、暗黒ドゥーム界屈指の布陣で制作された。
Virgin Blackはオーケストラや聖歌隊をフィーチャーした荘厳なサウンドで知られていたが、Spiineはその儀式的なムードを受け継ぎつつ装飾を抑え、ギターを主体としたフューネラルドゥームへとシフト。Xenの表現豊かなスクリームとグロウルは、悲しみや痛み、絶望といった負の感情を容赦なく描き出し、冷酷で無慈悲な暗黒世界へと踏み込んでいる。
Spiine『Tetraptych』各曲レビュー
#1 “Myroblysiia”
フューネラルドゥーム風のロングトーンの合間に陰鬱なトレモロリフが顔を出し、ドゥームゲイズやポストロック、DSBMを思わせるアプローチを展開。イントロの哀しげなピアノとともに鳴り響くギターの音色は、まるでMONOが葬送曲を奏でているかのよう。ヘヴィなロングトーンが鳴り始めると、オーケストラの厳かな旋律とXenのドス黒い咆哮が重なり、リスナーを闇の深淵へと引きずり込む。容赦なき暗黒美に思わず戦慄すら覚える一曲。
#2 “Glaciial”
重苦しい圧殺ギターにXenのグロウルが交錯する暗鬱ドゥーム。後半に重厚なストリングスがひと時の光をもたらすが、それも束の間。SescaのギターとXenの咆哮が全てを黒く塗りつぶしていく。終盤の哀愁味あふれるギターワークは本作のハイライトの1つ。
#3 “Oubliiette”
トレモロリフが効果的に用いられ、フューネラルドゥームとDSBMの混血と呼べるサウンドを展開。オーケストラの重層的なテクスチャーと相まって、本作中で最も「Gaze」の要素を感じさせる一曲。
#4 “Wriithe”
亡者の呻きのような声で幕を開け、陰鬱で重苦しいリフが闇を這いずり回る。幽玄で静謐なブレイクを挟んで、わずかに光が差し込むも、すぐにブラックメタル風の爆走へと切り替わる。最後には再び葬送曲のような悲壮なメロディが舞い戻り、亡者たちの魂を奈落へと還していく。
「Tetraptych」=「4つのパネルから成る連作絵画」というタイトルが示す通り、全4曲で約1時間という濃密な構成も、暗黒音楽好きには格別のご褒美だ。
NorttやEvokenといった重鎮のリリースで沸く2025年のフューネラルドゥーム界に新たな傑作が誕生した。本作はフューネラルドゥームでありながら比較的メロディアスで聴きやすいため(当社比)、FVNERALSやPresence of Soulといった暗黒ドゥームゲイズ好きにもぜひチェックしてほしい。
なお、2025年12月2日付で Lena Abé(My Dying Bride) が正式にメンバーとして加入した。これは本プロジェクトが今後も継続されることを示すものであり、続報に注目したい。
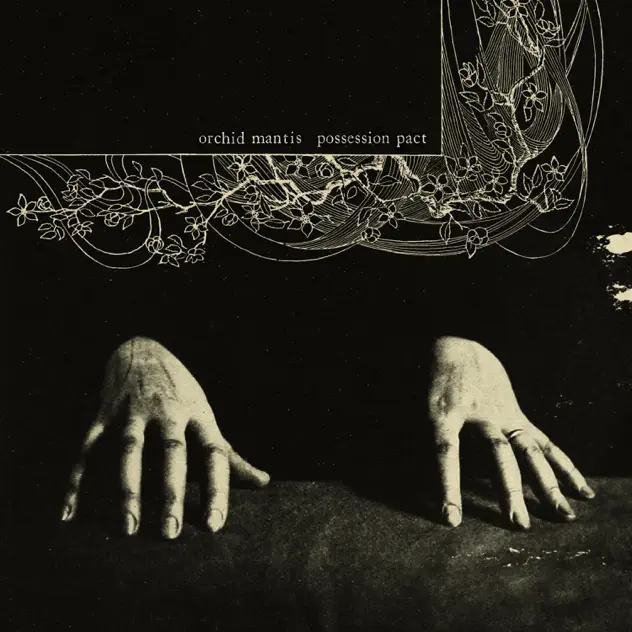
Orchid Mantis
Possession Pact
Orchid Mantis
Possession Pact
- release date /2025-04-25
- country /US
- gerne /Ambient, Dream Pop, Indie Pop, Slowcore
アトランタを拠点とするローファイ・ドリームポップ・アーティスト、Orchid Mantisの13thアルバム(※Spotify準拠)。
Orchid Mantisは、シンガーソングライターのThomas Howardによるソロ・プロジェクト。これまでローファイでノスタルジックなインディーポップ/アンビエントで多くのリスナーを夢見心地にしてきましたが、本作では作風を大きく変化させ、Low、Bedhead、Codeineといった90年代の陰鬱なスロウコアにフォーカスしています。
深いリバーブをまとったギターの音色は、宵闇にしたたる雨音のよう。そして削ぎ落とされたノーツの間から、Thomasの歌声が幽霊のように浮かび上がります。過去作が「草原でウトウトお昼寝」だとすれば、本作は「目覚めたら深夜の霊安室に安置されていた」くらいのギャップ。全編に渡って冷たくも甘美なメランコリーが満ちていて、じっくり落ちていきたい時にぴったりです。
イチオシは#4 “All The Passing Days”。葬送曲のような物悲しいメロディが、美しい思い出たちを静かに灰へと還していく。どの曲も徹底してスローテンポなので、人によっては平坦で退屈に感じるかもしれませんが、ボーカルものとインストがうまく配置され、ほどよい起伏が楽しめる点も好印象。
アートワークの時点でただならぬ雰囲気がありましたが、想像以上の変化で大興奮でした。2025年のドリームポップAOTY筆頭候補!
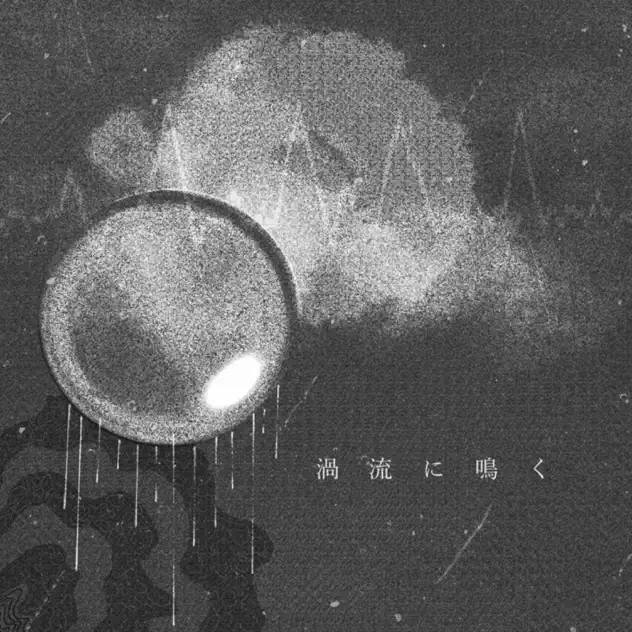
散▽巡
渦流に鳴く
散▽巡
渦流に鳴く
- release date /2025-03-29
- country /Japan
- gerne /Alternative Rock, Ambient, Grunge, Post-Rock, Shoegaze, Slowcore
大阪のシューゲイズ/オルタナティブロック・バンド、散▽巡(さんざめく)の1st EP。
2023年3月26日結成。本作の制作メンバーはぺん(ギター/ボーカル)、あかね(ギター)、しま(ベース)、yuyA(サポートドラム)の4名。
私が散▽巡を知ったのは2024年7月。東京初ライブの告知をきっかけに音源をチェックしたところ、そのダークな世界観に触れてたちまち虜になりました。
儚く繊細なパートはSigur Rós、ポエトリーリーディングと激情のダイナミズムはenvy、日本語で仄暗い情念を歌い上げる姿には天野月子がふと浮かんだりと、既存のシューゲイズに収まらない多彩な要素が絡み合い、独自の世界観を創り上げています。とりわけ静と動のダイナミズムは圧巻で、陽光きらめく草原から暗黒の深海までをも横断するような体験をリスナーにもたらします。
そして特筆すべきはぺん氏のボーカルの表現力。サウンドの起伏に沿って、母が子を寝かしつけるような優しい囁きや、轟音を切り裂くほどのエモーショナルな叫びも巧みに操り、語り手として強烈な存在感を放ちます。ぺん氏が紡ぐ歌詞も、哀しみや痛み、嘆きといった生々しい感情が渦を巻き、日本語ならではの陰影もあいまって聴く者の心を強く揺さぶります。
散▽巡『渦流に鳴く』各曲レビュー
#1 “光芒”
光が降り注ぐようなギターと儚げなウィスパーボイスが溶け合う美しいイントロダクション。
#2 “残鳴”
ポストロック風にゆったり進行しながら、徐々にボルテージを上げ、美轟音を解き放ちカタルシスを演出。
#3 “=rand(scp)”
陰鬱なメロディとともにノイズが激しく渦巻き、カマイタチのように全身を切り裂いていく。本作で最もダークな1曲。ちなみに読み方は「ダミースケープ」だそうです。※ぺん氏に教えていただきました
#4 “息吹”
トライバルなリズムによって陶酔へと誘う新境地的ナンバー。降り注ぐギターの美しさといったら、神々しさすら感じられるほど。
#5 “雫の中の彗星”
壊れそうなほど繊細なサウンドスケープに「知りたくなかった」のリフレインが切なく響く。突如轟音が波のように押し寄せたと思うと、また静寂が戻り、切なさをいっそう際立たせる。
#6 “浮遊” ※CD限定ボーナストラック
岡山のシューゲイズ・バンドlittle lamplightのギタリスト黒田麻衣を迎えた美轟音シューゲイズ。トリプルギターが織りなす重厚なテスクチャーと美しいメロディの融合はまさしくシューゲイズの真骨頂。この曲のためにCDをゲットする価値あり!
光と闇、静と動、美と狂気──そのすべてが渦流のように交錯する全6曲。散▽巡の美学を存分に味わえること間違いなし。
さらに会場限定で入手できるデモ音源には、『サンザメク』や『ニヒリズム』、『崩潰』といったライブの定番曲も多数収録。いずれも名曲なので、ライブに行かれる際はぜひゲットしてください。
本作リリース後に神崎渚(ドラム)が正式加入し、バンドが本格始動した今、「さんざめく」(ざわめき立つ)の言葉どおり、日本のシューゲイズ界を大いに賑わせてほしいですね。